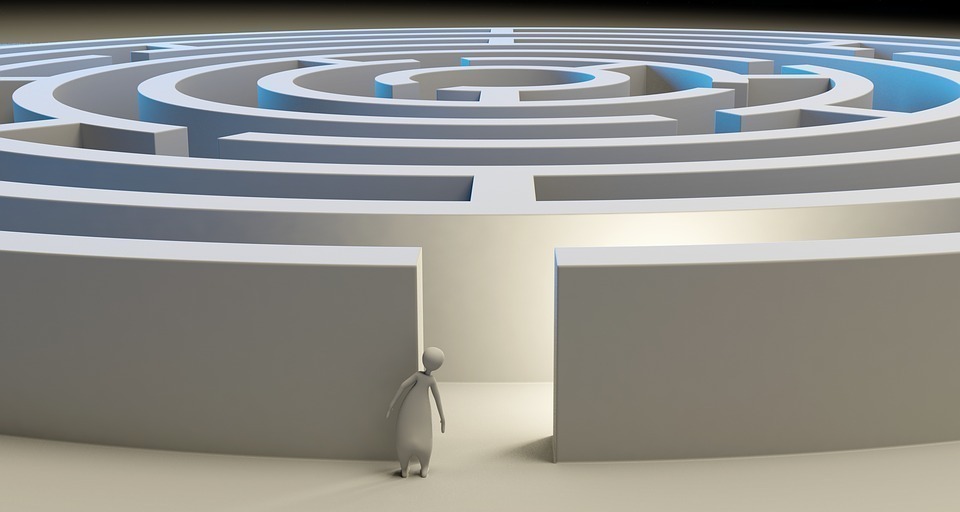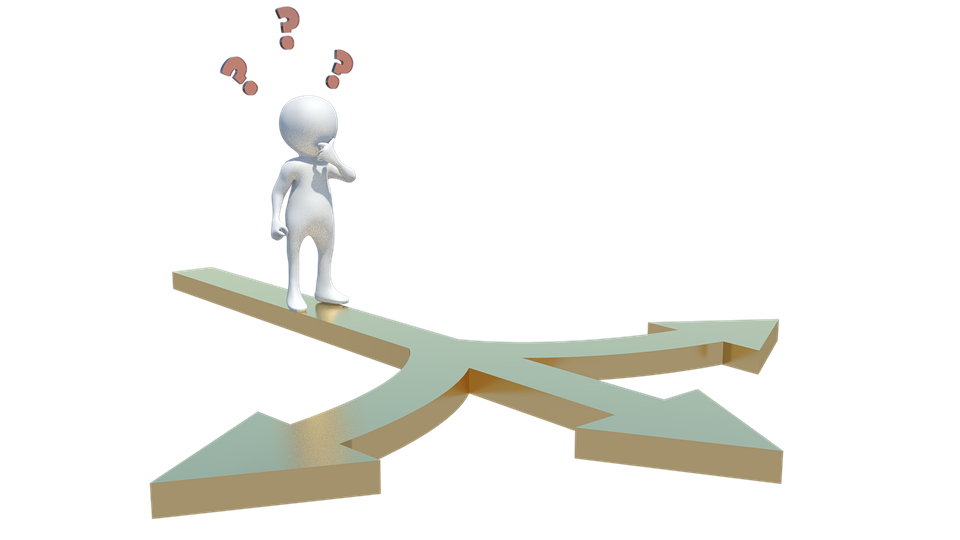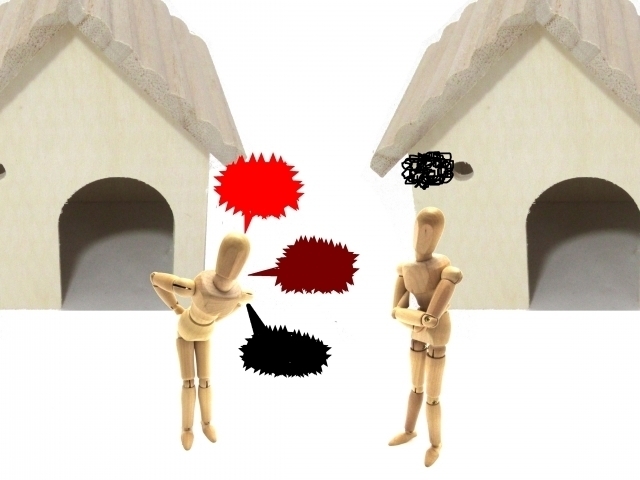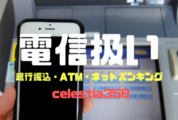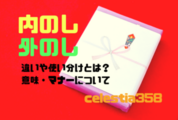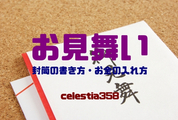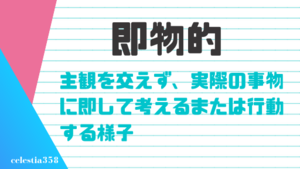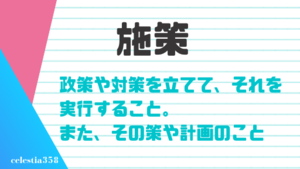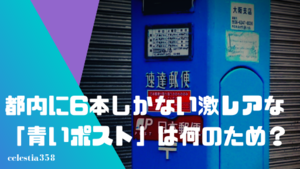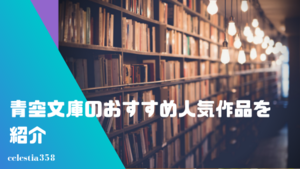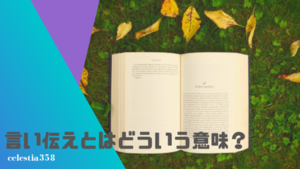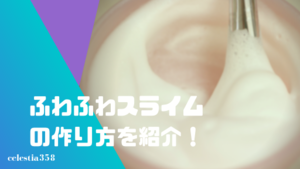「七面倒」とは?
「七面倒臭い」は俗っぽい印象を与えますが、江戸語辞典にも登場する古い用語です。
また、国語辞典や方言辞典にも語源や読み方が掲載されています。
「面倒」に一文字を加えただけの「七面倒」。
しかし、そのニュアンスは微妙に違います。
七面倒の意味と読み方は「しちめんどう」
「七面倒」の意味は“非常にわずらわしいこと”、これは「面倒」を強調した表現です。
読み方は「しちめんどう」。
「面倒くさい」を「めんどくさい」と口語で表現するように、「七面倒臭い」の読み方も「しちめんどくさい」と詰めて言うことがあります。
七面倒の由来や語源
「七面倒」の由来は、「面倒」の“手数がかかってわずらわしい、やっかい”という意味を強めるため、接頭語の「しち」を付けたものです。
「しち」は、わずらわしさの程度がはなはだしいことを示すときに用いる接頭語です。
同時に、“面倒で嫌になる”という気持ちをこめることができます。
(接頭) 形容詞や形容動詞の上に付いて、程度を強めるとともに、煩わしくていやだという気持を表わす。「しちくどい」「しちめんどくさい」「しちむずかしい」など。(精選 日本国語大辞典参照)
「しち」を付けた他の言葉、「しちむずかしい」や「しちやかましい」でも、非常にごたごたした状態を表す”ひどくむずかしい”や”たいそうやかましい”の意味に加えて、“不必要にむずかしい”、“むやみにやかましい”といった不快感を表現しています。
接頭語の「しち」は江戸時代以降に登場しました。
「しち」の音が変化して「ひち」とも言うようになり、現在は「しち面倒」「ひち面倒」のどちらも使います。
漢字の「七」は「しち」の音にあてはめた当て字にすぎないため、数字の七とは関係がありません。

「娘めが目を覚まし 邪魔ひろげば ひち面倒(娘が目を覚まして邪魔立てされたら厄介この上ない)」
これは1770年初演の浄瑠璃「神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)」での一節です。作者の福内鬼外(ふくちきがい)は江戸の才人、わたくし平賀源内のペンネームです。
「七面倒」は方言なの?
「七面倒」は厳密にいうと方言とはちがいます。
西関東の多摩弁や八王子弁ではとの説もありますが、これらの地域のみで使用されているわけではありません。国立国語研究所で茨城方言としていたり、方言辞典によってまるで記載がなかったりと、「七面倒」の扱いはまちまちです。
方言は時代につれて廃(すた)れたり、他の地域に移ったりします。
「県別方言感情表現辞典(2015年)」によると、「面倒くさい」に強調の「しち・ひち」をつけた「しち面倒くせー」は次の地域に分布しています。
- 北関東(栃木、群馬、埼玉、千葉)
- 和歌山県「しち面倒くさい」
- 広島県「しち面倒くさー」
- 長崎県「ひち面倒くさか」
- 熊本県「ひち面倒くさか」
七面倒くさいの使い方
- 確定申告の手続きはどうしても七面倒くさいことが多い。
- 入試の範囲は広すぎてあまりにも七面倒くさい気がします。
- 友人の話は七面倒くさい内容が多くうんざりしています。
- 補助金の申請は七面倒くさく簡単にはできません。
- 七面倒くさいことばかり言わずに素直に努力をすることも大切です。
「七面倒臭い(しちめんどくさい)」はどんなときに使う?
「七面倒臭い」の「七面倒」に添えられた「臭い」とは、「うさんくさい」「照れくさい」と同様に、好ましくない意味を強める働きをします。接頭語の「しち」と合わせると、”わずらわしい“の程度はさらに上昇し、”極めてわずらわしい“のレベルに達します。
「七面倒臭い」は形容詞であり、物の状態や性質を述語で言い表します。
【例文】
- 試験の範囲が広すぎて、全部覚えるのは七面倒臭い。
- あの人の作業はミスが多くてフォローしきれない、ええい、七面倒臭い。
【例文】
- (手順が異様に複雑な)七面倒臭い礼儀作法
- (例外がやたらに多い)七面倒臭い手続き
- (粗探しの得意な人間だらけの)七面倒臭い職場の人間関係
- (約束を守らない相手との)七面倒臭い交渉
「七面倒(しちめんどう)」の意味・由来・語源・読み方・使い方のまとめ
- 「七面倒」とはひどく面倒なこと。
- 接頭語の「しち(ひち)」で「面倒」を強調しているが「七は」当て字。
- 「七面倒」は方言辞典にも掲載されるが、国語辞典や古語辞典で扱われている一般的な用語。