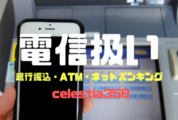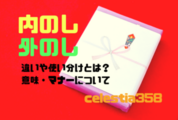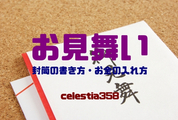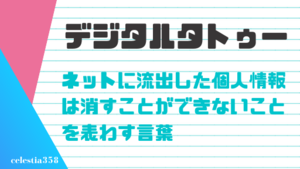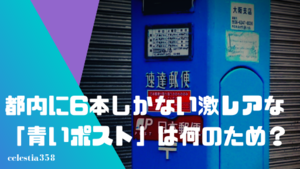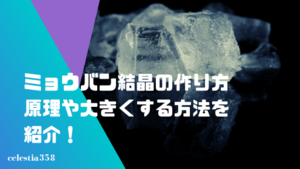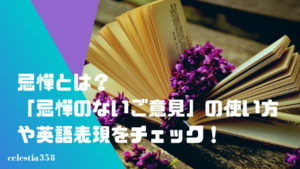運動会で流れるチェッコリの歌とは?
チェッコリとはそもそもどういう歌なのかピンとこない人のために、まずはその歌詞や発祥について紹介します。
ルーツ
チェッコリとは「Che Che Kule(チェッチェッコリ)」と名のつくアフリカ・ガーナの民謡で、おもに子どもの遊び歌として親しまれています。
日本で知られるようになったきっかけは、1957年のガールスカウト世界大会で披露されたチェッコリを、とある参加者が日本に持ち帰ったことです。
韓国語にもチェッコリという発音で「打ち上げ」の意味を表します。
以降、この民謡は踊りと合わせて「チェッコリダンス」として親しまれるようになります。
なお「チェッチェッコリ」という言葉に明確な意味はなく、日本でいう「せっせっせーのよいよいよい」とほぼ同義です。
代表者が歌ってから周囲の人達が復唱する、いわゆるエコーソングであり、日本でも「もりのくまさん」などで馴染みのある歌い方です。
ダンスも簡単で、リズムと歌に合わせて腰を左右に振りながら、両手を頭、肩、腰、膝、足首へと降ろしていきます。
最後のフレーズで両手を突き上げながらジャンプします。
足首までいくとかなり苦しい姿勢となりますが、とても盛り上がります。
●エコーソング=追っかけ歌のこと
歌詞
まずは原曲の歌詞をカタカナ表記で紹介します。
チェチェクレ チェチェクレ
チェチェ コフィンサ チェチェ コフィンサ
コフィンサ ランガ コフィンサ ランガ
カカ シランガ カカ シランガ
クム アデンデ クム アデンデ
クム アデンデ ヘイ!
次に、日本で親しまれている「チェッコリ」の歌詞を紹介します。
チェッチェッコリ チェッコリサ
リサンサマンガン(二酸化マンガン)
サンサマンガン(酸化マンガン)
ホンマンチェッチェッ!
原曲とは大分違うものの、発音が簡単になっているほか「二酸化マンガン」などの替え歌も存在するため、子供たちにはより親しみやすい歌詞となっています。
原曲の最後にある「ヘイ!」という掛け声に関しても、アメリカに伝わった時に加えられたという説もあり、チェッコリは歌も踊りも伝承の過程で大きく形を変えた民謡であるといえます。そもそも原曲の歌詞も具体的に意味のある言葉ではないので、難しく考えず地域の慣例に合わせて楽しみましょう。
以下に、桃太郎バージョンのチェッコリの動画を紹介していますので、可愛らしい振り付けをぜひご覧になってみてください。
チェッコリダンスの歌はなぜ運動会で流れる?
本項では運動会でチェッコリが踊られるようになったきっかけを、当時の人気アイドルグループによる影響も絡めて解説します。
運動会でチェッコリダンスで玉入れを始めたきっかけ
運動会の玉入れにチェッコリダンスが採用されたきっかけは、「スタート時のピストル音が聞こえづらい」という問題でした。そこでピストルの代わりとしてチェッコリダンスを踊り、歌詞が終わると同時に玉を入れ始めるという方式をとある学校が試したところ、これがメディアにも取り上げられるほど大ウケ。観客は踊りと玉入れを同時に楽しめ、児童もノリノリになることから、今では多くの学校の玉入れにチェッコリダンスが組み込まれています。
このように運動会におけるチェッコリダンスとは、競技を盛り上げる手段にとどまらず、きちんとした運営上の意味があるのです。なお発祥地については福岡や埼玉など諸説あり、詳しいことは明らかになっていません。
SMAPも踊ったチェッコリ体操
運動会でチェッコリダンスが踊られるようになったのは、おおよそ2000年代前半からといわれています。当時フジテレビで放送されていた「SMAP×SMAP」という番組では、「ザ・チェッコリーズ」というコーナーで木村拓哉さん・香取慎吾さん・稲垣吾郎さんの3人がチェッコリ体操を踊っていました。また2003年には「サッポロ・まる福茶」のCMソング用にチェッコリのカバー曲が作られるなど、様々な方面からチェッコリの名が広まっています。
こうしたチェッコリのメディア露出が学校関係者の知るところとなり、運動会での採用に至ったと考えるのが自然でしょう。
チェッコリ玉入れの発祥の地はどこから?
チェッコリ玉入れの発祥地について詳しいことは明らかになっていませんが、一説として名前を挙げられる地域はおもに福岡と埼玉の2県です。特に福岡は2014年時点で福岡市の小学校145校中、実に90校もの小学校でチェッコリ玉入れが導入されていたというデータもあり、チェッコリ玉入れ発祥の有力地となっています。
とはいえチェッコリは日本に伝わる過程で、既に原曲とは歌詞もダンスも似て非なるものに変貌しています。それと同じく、チェッコリ玉入れも全国で広まるにつれ学校単位で様式が変わっているため、確固たるルーツがあったとしても当時のやり方にこだわる必要はないでしょう。
それでも、近日中にチェッコリ玉入れの予定があり「右も左も分からないのは不安!」という方のために、ほとんどの学校で共通している手順を簡単に解説します。
チェッコリ玉入れのルール
チェッコリ玉入れのルールはおおむね以下の通りです。
① 玉入れのカゴを中心にして円を組む
② 曲に合わせて踊る
③ 歌詞が切れると同時に玉入れを開始(曲は流れ続ける)
④ 再び歌詞パートに入ると、玉入れを中止して①に戻る
⑤ ①~④を2、3回ほど繰り返す
ダンスの振付は学校によって大きく異なり、ガーナの伝統的な踊り方を踏襲しているものから、腰を振るだけのシンプルなものまで多種多様です。一方で競技中に使用される音源はもっぱら「ヒットヒットマーチ2014」であり、同CDには玉入れ競技専用の「チェッチェッコリ」が収録されています。
ほかにもあるダンス玉入れ
ダンス玉入れにはチェッコリのみならず、人気アーティストやアイドルグループのヒット曲を使う学校も数多くあります。チェッコリに比べてダンスがより本格的になるため、おもに高学年の競技や保護者参加プログラムとして催されることが多いです。またダンスとは少し異なりますが、玉入れのカゴを人が背負ったまま逃げ回る「移動玉入れ」という種目も運動会で人気のプログラムです。
玉入れはそのままでも十分に見応えのある競技ですが、チェッコリなどのダンス要素を加えることで見る方もやる方も、更に盛り上がること間違いありません。
チェッコリは、日本に伝わる過程で、原曲とは歌詞もダンスも変化してきました。また、地域や学校によっても、歌詞やダンスのバリエーションがあります。
チェッコリとは?運動会で聞く「チェッチェッコリ」のルーツや歌詞についてのまとめ
- ガーナ発祥の子供向け民謡で、日本に伝わってからは歌詞を変えて親しまれている。
- 運動会で使われるようになったのは2000年前半ごろで、「スタート時のピストル音が聞こえづらい」という問題がきっかけ。また当時、チェッコリのメディア露出が多かったことも関係している。
- チェッコリ玉入れのルールはまず歌詞に合わせて踊り、歌詞が途切れている間に玉入れを行い、これを2~3回繰り返す。なお、ダンスの振付は学校によってまちまち。